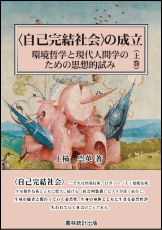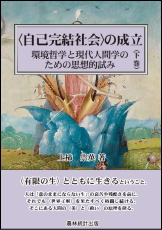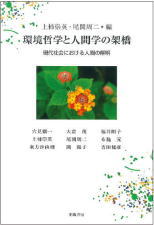『〈自己完結社会〉の成立』(下巻)
【第十章】最終考察――人間の未来と〈有限の生〉
(8)結論
さて、以上を通じてわれわれは予定していたすべての議論を終えることができた。ここでは最後に、本書が到達した結論に相当するいくつかの論点について整理しておくことにしたい。
まず、われわれの議論の出発点は、〈生の自己完結化〉や〈生の脱身体化〉を含む、〈自己完結社会〉の成立について分析していくことにあった。吉田健彦は、現代社会を「必然的異常社会」と呼んだが、このことはわれわれの議論においても示唆に富むものだと言えるだろう(84)。
すなわち〈自己完結社会〉の成立は、一方ではわれわれの根源的な本性とも深く結びつくという意味において、確かにある種の「必然性」を伴っているということ、しかし他方で、それがかつてないほどの人間の存在様式の変容を伴うという意味においては、そこにはやはりある種の「異常」な事態が生じているとも言えるからである。
そして本書において、〈関係性の病理〉や〈生の混乱〉と呼んできたものこそ、そうした「異常」がこの社会に具体的な形となって現れてきたものであった。
実際今日のわれわれは、他者との関係性に多大な困難を抱え、自らが生きる意味をめぐって多大な戸惑いを抱えていると言えるだろう。だが、本書が繰り返し指摘してきたのは、それらの背景となっている〈生の自己完結化〉や〈生の脱身体化〉を望んでいるのもまた、他でもないわれわれ自身であるということであった。
ここで改めて考えてみてほしい。はたしてわれわれは、本当に〈自己完結社会〉から抜けだしたいと思っているのだろうか。
例えば、〈自己完結社会〉から解放される最も確実な方法は、われわれがこの社会を覆う巨大な「インフラ」から「降りる」という選択をすることだろう。つまり〈社会的装置〉への依存を極力回避し、〈生〉を実現していくための諸契機を、主として直接的な人間関係の力によって実現するよう社会構造を組み替えていくことである。
それは巨視的に見れば、一度は自立化した〈社会的装置〉を解体させ、それを再び〈生活世界〉に埋め戻していくことであるとも言えるだろう。だが、おそらくわれわれは、そうした道など本心ではまったく望んでいない。
われわれはいまでも、〈社会的装置〉が与えてくれる〈ユーザー〉としての「自由」や「平等」を謳歌していたいし、そこにある「意のままになる生」や「自分だけの世界」を手放すぐらいなら、〈社会的装置〉から「降りる」ことも、それどころか自らの力によって“自治”を実現していくことさえも望んでいないのである(85)。
われわれの目の前にある〈自己完結社会〉は、例えば政治権力による独裁の骨肉化、管理社会の進展といったものとはまったく異質な側面を持つ事態である(86)。なぜなら〈社会的装置〉の発達そのものについて言えば、それはある面ではわれわれ自身が望んできた「存在論的自由」の実現、われわれが思う「本来の人間」=「完全な人間」を実現させるためにこそ必要なものだったからである。
おそらくわれわれは、この〈自己完結社会〉へと向かう時代の流れを止めることはできないだろう。われわれが「意のままになる他者」や「意のままになる身体」を求める限り、〈社会的装置〉はますます高度に発達し、〈生の自己完結化〉と〈生の脱身体化〉もまた、止めどなく進展していくことになるからである。
【第一章】で見てきたように、〈自己完結社会〉の未来については、大きく二つのシナリオが想定できる。
第一は、地球の有限性を含むさまざまな要因によって、〈社会的装置〉そのものが崩壊し、われわれが否応なく〈ユーザー〉であることから「降り」ざるをえなくなるという未来である。そして第二は、われわれが地球の有限性でさえも科学技術によって制圧してしまい、それによって究極の〈自己完結社会〉が実現してしまう未来である。
本書で見てきたように、第一の未来に待っているのは、〈共同〉の能力を喪失したかつての〈ユーザー〉たちが、荒廃しきった惑星にただただ無造作に放りだされるという事態、そして第二の未来に待っているのは、人体改造がもたらす「究極の平等社会」、「意のままになる他者」を演じてくれるアンドロイド、果ては「脳人間」と「自殺の権利」であった。
われわれは、はたしてどちらの未来へと向かっているだろうか。現時点で言えることは、われわれはこのいずれの未来に対しても、いまから備えをしておくべきだということ、そして少なくとも現時点のわれわれにはまだ、第三や第四の未来を追求できるだけの余地が残されているということだけである。
加えて本書が「人間とは何か」という根源的な問いと向き合いつつ、最後にたどり着いたのは「世界観=人間観」という視座であった。それは先の「必然性」とは別の次元において、〈自己完結社会〉の到来を決定づけたものこそ、あの〈無限の生〉の「世界観=人間観」だったと考えているからである(87)。
そして現代を生きるわれわれの苦しみの根底にあるものもまた、そうした「世界観=人間観」がもたらす現実否定の「無間地獄」、そうした理想と人間的現実との間に開いた途轍もない乖離なのであった。
かつてA・コジェーヴ(A. Kojève)は、近代的な人間の理想が滅び去るとき、歴史は終焉し、人間は再び動物になるのだと説明した(88)。だがその実態は、一時代の狂騒的な理想主義が現実に対して敗北したというだけのことでしかない。
われわれはそこで、「本来の人間」=「完全な人間」という名の白昼夢からようやく目覚めたのであって、むしろこうして現実の人間存在へと戻ってきたのである。したがって〈有限の生〉とともに生きるということ――それが、われわれが長い考察のなかから導きだしたひとつの答えなのであった。
もちろん本書が〈生活世界〉の構造転換について繰り返し描き、強い表現で〈共同〉の人間的基盤の解体を論じたからといって、例えば「過ぎ去った時代のなかにこそ真の人間の生活があった」などと主張したいわけではない(89)。
また本書が〈世界了解〉を強調したからといって、「現実との格闘は無意味であり、諦めて周囲のなすがままに生きよ」と主張したいわけでも、逆に「あなたが変われば世界も変わる」などと主張しているつもりも毛頭ない(90)。
加えて確かに、ここで述べてきたことが、直ちに〈関係性の病理〉や〈生の混乱〉、あるいは〈自己完結社会〉に伴う諸問題を解決するということにもならないだろう(91)。
では、本書の意義とは結局どこにあったと言えるのだろうか。このことを考えるために、われわれは再び本書の根底に流れるもうひとつの問題意識、すなわち人文科学的な知のあり方、とりわけ“哲学”の果たすべき役割とは何か、という問題に立ち返ってみたい。
【序論】で触れたように、これまで“哲学”と呼ばれてきたものは、揺るぎない答えを絶えず求める「絶対的普遍主義」に依拠するものであった。そしてその試みは確かに卓越したものではあったが、文献学的な意味での精密さや体系性に注力するあまり、またいかなる批判をも反駁しうる鉄壁な論理を構築しようとするあまり、どこか“哲学”の果たしうる重要な役割を素通りしているように見えるのであった(92)。
例えばここで、改めて問いかけてみたい。われわれが必要としているのは、本当に揺るぎのない偉人の言葉や、一切の綻びがない完全無欠な論理といったものだったのだろうか。そうではなくて、それは「意のままにならない生」の現実にあって、われわれ自身が自らの挫折や苦しみと寄り添いながら、それでも目の前の〈生〉を肯定し、前を向いて生きていくための術ではなかっただろうか。
自身はどこに立っているのか、自身は何を持っているのか、そして自身の足はどこを向いているのか。移りゆく世界のなかで、われわれはその大切な立ち位置を簡単に見失ってしまう。それを確認していく手がかりとなる意味や言葉こそ、われわれが本当に必要としているものではなかっただろうか、と。
「絶対的普遍主義」を求めることは、どこかあの「皇帝」と似ているように筆者は思う。そこに苦しみがあるとするなら、それは「永遠の命」を得られないといって自縄自縛に苦しんでいた「皇帝」の苦しみと本質的に同じものだからである(93)。
われわれは【序論】において、たとえ「絶対的普遍主義」に依拠することがなくとも、“哲学”には特別な役割があると述べた。それは、われわれが事物の認識や思考に先立って持っている基礎概念を分析し、それを整備していくこと、それによって人文科学的な知そのものを下支えしていく役割である。
しかし、おそらくそれだけではないのである。哲学とはやはり、〈思想〉のひとつの表現なのであって、必ずしも言語を用いない〈芸術〉とは異なり、それは徹底して言語を行使し、かつ構造化された理論を通じて〈思想〉を表現していく営為なのである。
そうした〈哲学〉にとって重要なことは、「人間とは何か」という最も根源的な問いにまで遡り、この現実を生きる人間存在を、新たな基礎概念を通じて説明していくこと、さらにはそれらをひとつの体系的な世界観、人間観にまで昇華させていくことであると言えるだろう。
例えば本書では、理性、自由、平等、権利、連帯、正義、権力、抑圧、資本主義、全体主義といった従来の基礎概念を避け、敢えて代わりに〈環境〉、〈生〉、〈関係性〉、〈生存〉、〈継承〉、〈間柄〉、〈共同〉、〈役割〉、〈信頼〉、〈許し〉、〈悪〉、〈救い〉、〈美〉といった、独自の基礎概念を整備するよう試みてきた。
それは本書が、〈自己完結社会〉というまったく新しい人間的現実と向き合うためであると同時に、〈無限の生〉の「世界観=人間観」を相対化できるだけの新たな立ち位置を必要としているためでもあった。
しかしそこで何より意識されていたのは、筆者自身がこの時代を生きるひとりの人間として、ひとつの〈思想〉の創造を実践すること、それをひとつの世界観、人間観という形で提示していくことだったのである。
われわれは【序論】で、この試みを「現代人間学」と呼んだ。本書が目指してきたのは、自らがこの新たな哲学的方法論の具体的な一実践例となることでもあったのである。
〈思想〉とは、世界や他者との対峙を避けられない人間が、自身の宿命と向き合おうとして紡ぎだしてきた意味や言葉を原点とするもの、そしてそれが世代を越えた目なざしのもとで体系化されたもののことを言う。
本書の概念を用いて言うなら、それは「人間存在が〈存在の連なり〉のもと、〈世界了解〉を成し遂げようと現実と格闘し、そのなかで生みだしてきた、世界や人間を説明するための体系化された意味や言葉」に他ならない。
われわれは【序論】において、〈思想〉の実践が優れたものになるためには、それが「強度を備えた〈思想〉」とならなければならないこと、そのためには理論としての巧妙さ、論理的な説得力を追求するだけでは不十分であるということについて述べてきた。
したがって本書の実践が成功したと言えるかどうかは、ひとえに本書の試みが「強度を備えた〈思想〉」に値する何ものかになりえたかどうかにあるだろう。はたして本書が、人間存在の本質を的確な形で掌握するものになっていたのか、そこから導出される意味や言葉が、この時代を生きることへのひとつの〈救い〉にまで触れえるものだったのか、そしてその言葉のなかに筆者自身の“美意識”が表現されていたのかどうかである。その判断は、後に続く人々に任せることにしたい。
【補論一】 残された課題としての〈文化〉への問い へ進む
【下巻】目次 へ戻る
(84)吉田(2016)。
(85)われわれは、〈ユーザー〉として得られる便益を思えば、〈ユーザー〉として負うべき自己責任など難なく受け入れることができる。そして〈社会的装置〉が適切に機能し、「〈ユーザー〉としての生」が適切に運用されていると思える限り、〈社会的装置〉の存在自体を気にかけることもないだろう。われわれが求めているのは、〈社会的装置〉の「良き運営者」――それが人間であろうと、ロボットであろうと関係なく――であって、それはわれわれ自身が「運営者」となることを必ずしも意味していないのである。おそらく多くの人々は、主体性を持って「運営」に関わるということが、〈ユーザー〉としての居心地の良さをかえって損なうことになると考えている。「自分だけの世界」こそを至上とする人々にとって、そこにあるのは無関心というよりも、“自治”を担うことへの意味の不在なのである。
(86)例えば近年の情報技術は、あらゆる個人情報や行動記録をビッグデータとして蓄積し、それを政治権力が活用していく道を開いた側面がある。そこからわれわれは、一連の事態をつい「新しい管理社会」といったおなじみの枠組みのなかで捉えてしまうかもしれない。しかしそうした理解の枠組みからは、〈自己完結社会〉をめぐる重要な論点はいずれも埋没してしまうだろう。〈自己完結社会〉は、政治権力によって「利用」されることがあるかもしれない。とはいえ問題にすべき本質は別のところにあるのである。
(87)これまでの議論で見てきたように、〈自己完結社会〉が人間の本性にその根を持つのは、あくまでわれわれが「人為的生態系」としての〈社会〉を創出し、それを次世代へと絶えず継承させてきたという事実、あるいはわれわれが現実との格闘に際して、絶えずより良き〈生〉を希求してきたという事実の部分に過ぎない。〈無限の生〉の「世界観=人間観」は、その繰り返される営みに新たな意味を付与することによって、そこに多大な質的変容をもたらしたのである。
(88)コジェーヴ(1987:244-247)、Kojève(1968:509-511)。
(89)人間は「人為的生態系」としての〈社会〉を生みだし、それを継承していく機構を備えて以来、その中心に〈有限の生〉の理を秘めつつも、常に変わりゆく存在となった。そしてその歴史は常に一方通行であって、われわれは未来に何かを託すことはできても、その逆に向かうことなど決してできないだろう。われわれが過去に目を向けるのは、特定の時代を称揚したり、そこにある種の理想を見いだしたりするためではない。それはあくまで、自らが生きる時代の本質を見つめ、未来に託すべき何ものかを考察するための参照点を得るためである。
(90)〈世界了解〉は、〈有限の生〉=「意のままにならない生」の現実を引き受け、自らの置かれた等身大の現実との格闘を通じて、より良き〈生〉を希求していく礎となるものである。したがってそれは、単なる「敗北主義」や「諦め主義」とはまったく別のものであると言える。とはいえ〈世界了解〉さえ達成できれば、それですべてが上手くいくと考えるのもまた誤りである。〈世界了解〉はあくまで土台に過ぎず、現実との格闘がなければ、われわれは結局何ひとつ成し遂げることなどできないからである。もちろんそうした格闘の結果、本当により良き〈生〉が実現できるかどうかなど誰にも分からない。それでもなお格闘すること。現実から離れた理念を持ちだすことなく、あくまで現実から出発し、そこからより良き〈生〉を希求し続けること。これこそが〈有限の生〉とともに生きるということの真意だろう。
(91)そもそも、われわれが口にしている「問題解決」とは何だろうか。有限な存在として生きるわれわれの理からすれば、“解決”以前に何事かを“問題”として提起すること、加えてそれが何ゆえ“問題”だと言えるのかを説明すること自体が容易なことではない。そうした意味においては、本書の目的は、そもそも「問題解決」ではないとも言える。〈哲学〉が格闘すべき領域は、それとは別の所にあると考えているからである。
(92)【序論】でも触れたように、筆者は明治期以来のわが国の「翻訳文化」や、従来の哲学が果たしてきた多大な貢献については十分に理解しているつもりである。本書では、そのことを踏まえてもなお、そこには欠けているものがあったと主張したいのである
(93)「大きな物語」は死んだ、と主張したのは「ポストモダン論」であったが、その後継者たちが、はたして本当に「絶対的普遍主義」のドグマを克服したと言えるのかどうかについては意見が分かれる部分だろう。例えばそこで、彼らが〈思想〉を論じることには意味がない、体系的な理論を構築すること自体に意味がないと考えているのであれば、それはむしろ、彼らが未だに「絶対的普遍主義」の呪縛から解放されていないということの証左であるとも言える。いかなる言説も信頼に値しないという過度な悲壮感は、実際には絶対的な何ものかの存在を信じたいという心の裏返しであるとも言えるからである。