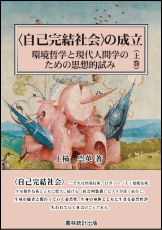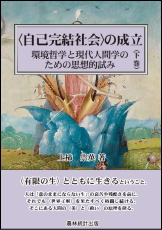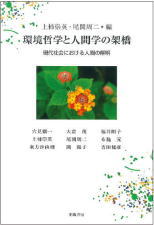『〈自己完結社会〉の成立』(下巻)
【補論1】残された課題としての〈文化〉への問い
ここからは、本書に残された課題について言及しておくことにしよう。まず、本書が構築してきた理論的な枠組みについては、すでにいくつかの課題が明らかになっている。
例えば【第二部】および【第三部】で見た、「〈生〉の舞台装置」としての〈社会〉の構成成分としての、「社会的制度」と「意味体系=世界像」を隔てるものとは何か、また両者が本当に区別可能なものだと言えるのか、あるいは【第四部】で見た〈間柄〉や「〈我‐汝〉の関係性」の枠組みと、〈役割〉、〈信頼〉、〈許し〉を結びつける諸概念の立体的構造とはいかなるものか、また「不介入の倫理」は、それ自体でひとつの〈間柄〉の形であるとは言えないのか、といった問題がそうである。
加えて本書では、西洋近代哲学のなかに「〈生存〉軽視の伝統」や〈無限の生〉の「世界観=人間観」を見いだしてきたわけだが、その文献学的な裏付けは必ずしも十分なものとは言えないだろう。
しかしこうした「些細」な課題、あるいは本書を補強するための課題についてはこれぐらいにしておこう。ここで触れておきたいのは、〈思想〉の実践という、より大きな文脈において導出される課題であり、本書では十分に言及しきれなかった論点についてである。
それは、端的に言えば〈文化〉をめぐる問題についてである。例えばわれわれは【第九章】において、日本社会がたどった150年あまりを振り返りつつ、「第四期」以降の時代において、この社会に「諦め」に満ちた虚無の情念がますます拡大していったこと、また「戦後思想」の問題として、とりわけ〈自立した個人〉を頂点とする「第二期」以来の人間の思想に代わるものを、われわれがついに構築できなかったことについて見てきただろう。
筆者が危惧しているのは、こうした「諦め」の蔓延や人文科学の低迷を背景として、これまでわれわれが体験したことのない水準での「文化の衰退」とも呼ぶべきものが生じているのではないかということである。
だがそれ以前に、そもそも“文化”とは何だろうか(1)。例えばわれわれは“文化”というものを、「欧米人は玄関で靴を脱がない」といった行動様式や、「わび・さび」といった伝統的とされる観念、あるいは法隆寺や万葉集といった文化財、アニメからアイドルに至るまでの大衆消費財などと同じものだと考えている。
しかしこうした文化観は、文化をあたかも芸術(作品)のように固定化したものと見なす――「鑑賞としての美」ならぬ――「鑑賞としての文化」に過ぎないだろう。
本書がここで論じようとしている〈文化〉の概念とは、それとはまったく異なるものである。例えば〈美〉が人心に働きかけ、人々を動かす力を持つものだとするなら、ここでの〈文化〉とは、人間精神に働きかけ、人々の行動に意味を与える力を持つものだと言える。
なぜならここでの〈文化〉とは、人々が有限な存在として世界や他者に向き合ってきた記憶の地層であるとともに、そのなかで形作られてきた“知恵”や“感情”や“美意識”などが集積したもののことを指しているからである。
例えばここに一体の木像があるとしよう。ここでわれわれが、その木像の歴史的、造形的、審美的価値について専門知を披露したところで、はたしてここで言う〈文化〉を理解したことになるのだろうか。そうした態度は、むしろ最も表面的な次元での「鑑賞としての文化」だと言えるだろう。
なぜならそうした態度を通じて、われわれが自身の生き方、あり方に対して新たな意味を獲得する余地などほとんどないからである。そうではなくて、例えばわれわれはその木像から、それを彫りあげたひとりの人間の姿を思うことができるだろう。それだけではない。それから数100年もの間、それを見つめ、それに何かの思いを託そうとしてきた人々の姿、あるいはそれを保存し、後世にまで残そうとしてきた人々の姿など、われわれは木像とともにあった無数の〈生〉のことを思うことができる。
そしてそこから、それぞれの時代に、それぞれの人々が行ってきた現実との格闘の記憶、〈生〉の実現と〈世界了解〉とをめぐって、そこにいかなる知恵や、感情や、美意識があったのかということを思うことができるのである。
すなわち、われわれが何ものかを通じて、〈連なり〉の先にある人間の生き方、あり方そのものと出会うということ、そしてそこからわれわれ自身の生き方、あり方を再び思うということ、その積み重ねこそが――われわれが【第九章】において「生きた地平に立つ」と呼んできたものと同じように――おそらく真の意味において〈文化〉を理解することにつながるのではないか、ということなのである。
したがってもし、「強度のある〈文化〉」や、「潜在力の高い〈文化〉」といったものがあるとするなら、そこに求められる条件とは次の二つになるだろう。
まずひとつ目は、そうした事物の背後にあって「目には見えないもの」に触れることができる想像力を、〈文化〉の担い手となる人々が、人間集団としてどれだけ保持しているのかということ、そしてもうひとつは、その人間集団が、そうした想像力を引きだすための記憶の地層をどれだけ引き継ぎ、保持しているのかということである。
本書で先に「文化の衰退」と述べたのは、実はこうした「不可視の間(あわい)を見通す目」や「記憶の蓄積と継承」という〈文化〉を支える二つの基盤が、いずれもこの社会ではきわめて脆弱なものになっていると思われるからなのである。
例えば今日、われわれはどこか「目に見えるもの」だけが、そのまま世界そのものであるかのように誤解してはいないだろうか。今日世間で流通しているさまざまな作品のなかでも、とりわけ目につくのは「直接的」な態度や表現である(2)。そしてその典型とも言えるものは、人が泣いていれば悲しんでいると考え、笑っていれば楽しんでいると見なすかような安易な目なざしだろう。
考えてもみてほしい。ここに「笑っている」人間がいるとして、その人は本当に「楽しい」から「笑っている」と言えるのだろうか。例えば人間には、ひとりが「悲しい」と口にしてしまえば、皆が立ちあがれなくなるときがある。そうしたとき、人は敢えて「笑おう」とするのである。それは嘘や欺瞞ではなく、「意のままにならない世界」を生きるための人間の知恵である(3)。
しかしそこには、まったく別の種類の「哀しさ」があるのである。それは「悲しくても笑わなければならない」という、人間そのものの「哀しみ」に他ならない。だがそうした「哀しみ」のなかでも、人は「笑う」。為す術がないときには、ときにどうしようもなく「笑ってしまう」のが人間だからである。
またわれわれはどこかで、すべての存在に対して理由を求め、しかもそれらをいちいち言葉で説明できなければならないと考えてはいないだろうか(4)。メリット/デメリットの損得計算によって結論を急ぎ、「白か黒か」で語れないもの、理にかなう説明が困難なものには、そもそも存在する意味などないとさえ考えているのではないだろうか(5)。
正解がないという状態に耐えられないし、世界の曖昧さに身を置くことにも耐えられない。そしてそれは図らずもわれわれが、「不可視の間」と向き合うことが困難となっている現実、「目に見えないもの」に働きかけ、自ら「目に見えない世界」を構築していく力を失いつつあることを物語っているようにも思えるのである(6)。
加えて今日、われわれは自身の存在に直結する古の人々の記憶を、ほとんど意識することなく過ごしている。その意味においては、われわれが“日本文化”と呼ぶものこそ、まさしく「鑑賞としての文化」の権化とでも言うべき代物ではないだろうか。
例えばわれわれは、いまでも和歌や枯山水を引き合いに出して、容易に日本的美意識を論じている。しかしその関心は、はたして知的な関心の向こう側に、古の人々が直面していたはずの現実や格闘の記憶といったものにまで及んでいると言えるのだろうか。
及んでいないとするならば、それは「現代アート」と同じく単なる鑑賞物であって、人間の生き方、あり方の問題とは切り離された、やはり「鑑賞としての文化」に過ぎないのである。
またそうした態度は、われわれの形骸化した“伝統”概念にも現れている。例えばある人々は、何ものかが過去から長く続いているという事実だけをもって、その伝統は価値があると主張し、またある人々は、何ものかが比較的近年に成立したという事実だけをもって、その伝統は偽物であると主張する。
しかし先の〈文化〉の概念からすれば、このいずれもが見失っているものがある。それは、そこに何ものかを継承すべき価値あるものだと考え、多くの労力を払ってまでそれを保存してきた人々がいるという事実そのものである。
ここでわれわれが注視すべきことは、そこにいかなる人々の知恵があり、感情があり、美意識があったのかということの方だろう。ここから明らかとなるのは、たとえ一世代であろうとも、そこに何かを継承しようとする人々の意思があったとするなら、そこには「伝統」と呼びうる何かがあるということである(7)。
この文脈において危惧されるのは、われわれがとりわけ「第二期」になって、「悪しき戦前」をめぐる否定的な感情から、過去の「記憶の地層」を意図的に断絶してきた側面がなかったのかということである。
とりわけ現代人に直結するこの150年の記憶、そこにあったはずの人々の格闘の記憶や、知恵や感情や美意識の記憶をなかったものとし、それを単なる鑑賞の慰みものとして扱ってきた側面は本当になかったのかということである(8)。
そうだとすれば、そこにあるのは単なる〈文化〉の抜け殻であって、そこからはわれわれが自らの現実と格闘していくいかなる意味も想起されはしないだろう。
過去の時代に思いを馳せるということは、過去に生じた何ものかを正当化するということではない。【第九章】でも見てきたように、歴史を「意味のある過去」として理解するためには、それを善悪正誤や現在の尺度によって裁断することなく、あくまで事実を事実として直視していくことが求められるのである。
もしもわれわれが、過去の記憶を意図的に隠蔽、断絶させようとするのであれば、それは言ってみれば〈文化〉的な“自死”に等しいだろう。
いずれにしても、われわれの社会が「目に見えるもの」だけを真実とし、「目には見えないもの」を見通す力を失うなら、そして過去の人々が蓄積してきた記憶を蔑ろにし、自らの生き方、あり方を照射していく足場を自ら閉ざすとするなら、われわれの未来は漆黒の暗闇でしかないだろう。
われわれは人間集団として、「不可視の間を見通す目」を鍛錬し、「記憶の蓄積と継承」という問題に真剣に向き合っていく必要がある。そしてそこに〈哲学〉が貢献すべきものがあるとするなら、それは軽薄な「鑑賞としての文化」を打ち破れるだけの、強度を備えた新しい“文化論”を構築していくことであると言えるのである。
【補論2】 学術的論点のための五つの考察 へ進む
【下巻】目次 へ戻る
(1)一般的な辞書によれば、“文化”とは、「①文徳で民を教化すること。②世の中が開けて生活が便利になること。文明開化。③(culture)人間が自然に手を加えて形成してきた物心両面の成果。衣食住をはじめ科学・技術・学問・芸術・道徳・宗教・政治など生活形成の様式と内容とを含む。文明とほぼ同義に用いられることが多いが、西洋では人間の精神的生活に関わるものを文化と呼び、技術的発展のニュアンスが強い文明と区別する」とある(『広辞苑』 2018)。
(2)ここで、筆者が「直接的な態度や表現」と述べたものにはさまざまな含みがある。本文でも言及しているように、例えば目に見えるものをそのままの形で受け取る、言葉を文字通りに受け取る、悲しいなら悲しみの感情をただただ流出させることがそのまま表現になることなど、これらに共通しているのは、いずれも人間的世界における目には見えない事物の間、ここで言う「不可視の間」が蔑ろにされていることである。“アーティスト”たちは、それを高度に婉曲的に表現することができるかもしれないが、そうした技巧的な問題と、「不可視の間」が捉えられているかどうかということは、本来まったく別の問題なのである。
(3)「ホリスティック教育」を提唱する吉田敦彦(1999、2009)は、自身のメキシコでの教育経験も踏まえたうえで、メキシコの人々に見られる楽天的な明るさを、脳天気な「漂白された明るさ」とは一線を画した、深い悲しみや陰影に裏打ちされた明るさ、「理性のコントロールで悪を制御できるとする理性主義的な楽観主義に深く絶望し悲観しているからこその、選び取られた楽観主義」であると指摘している(吉田 1999:51)。
(4)この、形式的な意味での言葉への過剰な依存は、先の「目に見えるものをそのまま世界そのものであると見なす態度」を別の角度から捉えたものだと言えるだろう。言葉とは本来、「目には見えないもの」を多大に背負って成立しえるものである。たとえ文法的に誤っていようと、言語としては聞き取れない呻きや囁きのようなものであったとしても、それらはときに言葉としての力や美しさを十分に備えうる(吉田 2017)。逆に形式的な言葉への依存とは、そうした言葉の背景に目を向けることなく、すべてを言葉で説明できると考え、また説明すべきだと考え、そして実際に説明しようと試みる態度であると言えるだろう。われわれは今日、あまりに多くの物事を言葉のまま、文字通りに受け取ることに慣れすぎている。しかし言葉の持つ真の力や美しさは、おそらくそうした態度からは生まれてくることはないのである。
(5)例えば今日散見されるのは、何事かを指して「それがなくてもデメリットはない」という表現である。われわれはここに、典型的な「不可視の間」に対する感受性の低さを感じ取ることができるだろう。それとは逆に、本書が主張するのは、「存在するものには必ず理由がある。目の前に事実として存在するものには、たとえそれがいかなるものであったとしても、かつては意味を持っていたか、あるいはわれわれが自覚していないだけでいまでも何らかの意味を備えている」という原則である。人間的世界の物事を「メリット/デメリット」で裁断しようとする態度は、それゆえ「不可視の間」と向き合う態度とは真逆のものだと言えるだろう。
(6)吉田健彦は言う。「現代科学文明とは、ある面において、「ノイズを追い払うことにより安全で無前提となった生において生じた空白をいかに埋めるか」という観点によって推し進められていく、そもそもが代替品の総体でしかないのかもしれない。我々はその代替品を、あたかも芸術、文化であるかのように思わされていく。静寂によって裏づけられてきた自然への畏怖、祖先との語らい、そういったものにより確固とした足場を持っていた芸術は、それ自体もまったくその内実を変性させていくだろう。そして音楽は、無為な無音を埋めるためだけの単なる騒音となる」(吉田 2018:236)。「不可視の間を見通す目」とは、ここで吉田の言う「存在論的ノイズ」を感受し、理解していく力であるとも言えるだろう。われわれに欠けているのは、そうした「空白」のなかでも、自ら意味を見いだしていく力、そしてより良き〈生〉となりうるわれわれなりの「答え」を導いていくための力なのである。
(7)もちろん「伝統」を論じるうえで、継承された時間の長さは重要な要素のひとつではある。だがそれは、起源が古いことそのものよりも、対象がそれだけ多くの時代や担い手のなかを経てきたという事実を伴うからこそ、重要であると言えるのである。
(8)かつて三島由紀夫は、『文化防衛論』(1968)において次のように述べたことがある。「文化主義とは一言を以てこれを覆えば、文化をその血みどろの母胎の生命や生殖行為から切り離して、何か喜ばしい人文主義的成果によって判断しようとする一傾向である。そこでは、文化とは何か無害で美しい、人類の共通財産であり、プラザの噴水の如きものである。……われわれが「文化を守る」というときに想像するものは、博物館的な死んだ文化と、天下太平の死んだ生活との二つである。その二つは融合され、安全に化合している」(三島 2006:34、36)。本書は、三島の文化論に対してすべての点において共感するわけではないが、われわれの薄弱な“文化観”を思うとき、この言葉は半世紀を経てもなお色褪せないものがあるように思える。