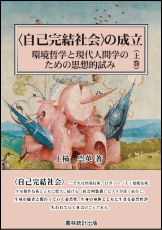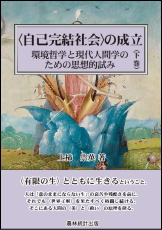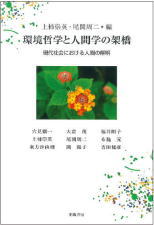『〈自己完結社会〉の成立』(下巻)
【第十章】最終考察――人間の未来と〈有限の生〉
(3)〈無限の生〉の「無間地獄」
われわれはこれまで、「意のままになる生」こそがあるべき人間の姿であると考える〈無限の生〉の「世界観=人間観」が、歴史的にいかなる形で展開してきたのかということについて見てきた。
ここからは、そうした「世界観=人間観」がなぜ悲劇的な帰結をもたらすのか、〈無限の生〉に内在している根源的な矛盾について見ていきたい。
前述したように、われわれは近代と呼ばれる時代を通じて、着実に「存在論的自由」を実現させてきたと言える。実際、自由、平等、自律、共生といった近代的な価値理念の数々は、いずれも「本来の人間」=「完全な人間」の名のもとに「存在論的自由」の拡大を要請していくものであった。
これらの価値理念が〈無限の生〉との間に深い連関性を備えていることは、それらが何より「現実に寄り添う理想」としてではなく、「現実を否定する理想」として語られてきたことにも良く現れているだろう。
「現実に寄り添う理想」とは、自身を取り巻く現実から出発し、それを引き受けた先にある、より良き生き方のための理想のことである。これに対して「現実を否定する理想」とは、想像された理念から出発し、理念に相応しくない現実そのものを克服しようとする理想のことを指している。
前者の理想が現実との格闘、現実との折り合いのなかから導出されるものだとすれば、後者の理想は、現実から離れた「あるべき人間」という地点に立って、本来無条件に与えられるべきものとして想起されるものだからである(18)。
確かに「現実を否定する理想」は、その準拠点が現実の外部に置かれることによって、しばしば現実を改変する強力な潜在力を発揮してきた(19)。しかしまさしくこうした性質ゆえに、その理想は深刻な矛盾にもまた直面してしまうのである。
例えば「存在論的自由」の理念は、われわれに「存在論的抑圧」からの解放を要求するだろう。しかし自らを拘束する「鉄鎖」をひとつ取り除いていく度に、おそらくわれわれは自身を縛るさらなる「鉄鎖」に気がつくのである。
そしてそこには終わりがない。というのも「存在論的自由」の理念は、ここで一切の「鉄鎖」に縛られることのない人間など存在しないという人間的現実を決して受け入れることができないからである。自由も、平等も、自律も、共生も、それらが「現実を否定する理想」として語られている限り、そこには同じ矛盾が内在することになる。
例えばわれわれが「不自由」をひとつ取り除けば、われわれはそこに新しい「不自由」を「発見」する。そして「不平等」をひとつ取り除けば、われわれはそこに新しい「不平等」を「発見」するだろう。
そうした理想は、「意のままになる生」という、決してたどり着くことのない「完全な人間」の物語に依拠している。そのため絶えず、現実を否定し続けていなければならないのである。それは言ってみれば、〈無限の生〉がもたらす「無間地獄」に他ならない(20)。
「完全な人間」を追い求める人々は、したがって目の前の不自由、不平等、非自律、非共生にばかり目を奪われてしまう。しかし繰り返すように、われわれが注目すべきことは、こうした終わりなき循環構造の傍らで、われわれが望んだ「理想世界」もまた、着実に具現化されてきたということである(21)。
例えば“自由”は、「自己責任」を伴うものの、〈生〉にあらゆる「自己実現」の機会が与えられるという形となって実現されてきた。また“平等”は、原則的には、すべての人間が同一条件のもとで〈社会的装置〉に接続できるという形となって実現されてきた。
“自律”は、生きることの「自己完結」を通じて、あらゆる対象を自ら考え、価値づけることができるという形となって実現されてきた。そして“共生”は、〈社会的装置〉を媒介としながら、また互いへの「不介入」を徹底することによって、差異を乗り越え、多様な価値観のもとで、人々が緩やかに結合できるものとして実現されてきたのである。
その実感がないというのであれば、【第九章】で見てきたように、100年前の人々がかつていかなる世界のもとで生きていたのかを想起してみると良い。ここで目を向けるべきことは、その理想の実現の不徹底さや不完全性ではなく(22)、むしろその理想が、いかにしてこの地上に具現化されてきたのかということの方である。
すなわちそれらが「〈ユーザー〉としての自由」、「〈ユーザー〉としての平等」、「〈ユーザー〉としての自律」、「〈ユーザー〉としての共生」といった形で、〈社会的装置〉の力を媒介として、はじめて実現されてきたという事実である。
このことは、今日われわれが享受している「自由」も、「平等」も、「自律」も、「共生」も、われわれが〈自己完結社会〉に接近することによってこそ成し遂げられた側面があるということを意味している。
そしてわれわれが「まだ足りない」といって、貪欲に「意のままになる生」を追い求める度に、われわれは一歩、また一歩とさらなる〈自己完結社会〉に向かって前進していくということもまた意味しているのである。
しかし〈無限の生〉の「世界観=人間観」がもたらす真の矛盾は、さらに次の地点にある。前述のように、それが顕在化を遂げるためには、〈生の自己完結化〉と〈生の脱身体化〉が本格的に進行する時代、爆発的な科学技術の展開に伴って、「意のままにならない生」の諸要素が文字通り取り除かれていく時代を待たなければならなかったからである。
それまで〈無限の生〉は、現実の分厚い壁に立ち阻まれ、その秘められた力を十全に発揮することができなかった。「現実を否定する理想」は、その理念が未だ現実味を欠いているうちは、人々に限られた影響しか及ぼさないからである。
しかし、変容したのは現実の方であった。実際われわれは、歴史的にはさほど遠くない過去において、住むべき場所、携わるべき仕事、あるいは関わるべき他者から、結婚、出産、子育てに至るまで、個人的な〈生〉を形作るあらゆる事柄が“自発性”と“自由選択”に基づくものへと移行していく時代を経験してきた。
そしてわれわれはいままさに、わが身に降りかかる「意のままにならない他者」や「意のままにならない身体」からの影響を、科学技術を通じてますます「意のままに」管理、コントロールできる時代へと移行しつつあるのである。
「現実を否定する理想」は、それが着実に具現化し、現実がその理念に近づいていくほどに、人々に強力な作用を及ぼすようになるだろう。こうしてある種の分水嶺を越えたとき、〈無限の生〉はついにその本領を発揮することになる(23)。
端的に言おう。そこでは「意のままになる生」こそが「正常」となり、「意のままにならない生」の現実は「非正常」として認識されるようになる(24)。自発性と自由選択が限りなく飽和していく世界のなかで、われわれを取り巻く「意のままにならないもの」たちは、やがてすべてが「不合理」で、「不当」で、「異常」なものとして認識されるようになるだろう。
「かけがえのないこの私」は、こうして「こうでなければならないこの私」となるのである。
だがまさにこの地点において、〈無限の生〉の真の矛盾が露わとなる。なぜならわれわれが人間である限り、たとえどれほど「意のままにならない他者」や「意のままにならない身体」から解放されて見えたとしても、そこには必ず「意のままにならないもの」が残されているからである。
ここでわれわれは、あの「不介入」の試みさえも、なぜ結局は挫折を余儀なくされたのかということを思いださなければならない。要するに、〈無限の生〉は必ず敗北する。ここにあるのは、「意のままになる生」をどこまでも希求した末に訪れる、〈無限の生〉の、現実というものに対する敗北なのである。
この恐るべき事態は何を意味しているのだろうか。ここではそのことを、ふたつの「寓話」に託しながら見ていこう。
- ・・・・・・あるところに、殺生に心を痛めるひとりの若者が住んでいた。彼は人間を、他の命を傷つける悪しき存在であると考え、自身がその「悪」に気づいてしまった以上、「悪」に屈することはできないと考えた。
若者が最初に行ったのは、動物たちの命を救うために、自ら一切の肉を食べないということであった。しかし意地悪な人間が若者に向かって言う。「あなたは他の命を傷つけないと誇らしげでいるが、あなたは植物を殺して食べているではないか」。
そこで若者は、今度は自ら野菜を食べることを禁じ、果実のみで生活することを決意した。なぜなら果実は「植物が動物に食べてもらうために自らもたらした恵み」であると若者は考えたからである。
ところが今度は、別の人間が彼に向かって言う。「あなたが食べている果実は、本当に植物があなたに食べてもらうために実らせたものなのか。果樹園などというものを造り、あなたは植物を自分自身に奉仕させている。それは虐待とは言わないのか」。
それを聞いた若者は言葉に詰まり、「他の命を傷つける」おのれの運命を呪いつつ、ついに痩せ衰えて死んでしまった(25)。
もうひとつは、ちょっとした「喜劇」の物語である。
-
- 先生「ここに熱した鉄の棒があります。あなたはこれを素手で持つことができますか。」
- 生徒「いいえ、持てません。そんなことをすれば大やけどをしてしまいます。」
- 先生「いや、人間は無限の可能性を持っているのです。今はとても実現しないと思えることでも、理想を捨てずに諦めなければ、どのようなことであってもいつかは実現するのです!」
- 生徒「でも、やっぱり熱いです。私にはできそうにありません。」 先生「それでは、身近なところからやってみましょう。それで、少しずつ変えていけばいいのです。」
- 生徒「なるほど! では、私もお風呂の温度を42℃に設定することから心がけます!」
まず、このふたつの「寓話」には、いずれも〈無限の生〉の矛盾が表現されている。最初に注目したいのは、両者が紛れもなく「現実を否定する理想」の物語であるということである。
例えば前者の「若者」は、他の命の犠牲を伴わない人間の生などありえないという現実を否定している。また後者の「先生」は、いかなる努力によっても人間の手は熱鉄を持つことなどできないという現実を否定しているからである。
いや、そうではないと思う読者もいるかもしれない。例えば先の「若者」は、他の命を犠牲にしなければならない人間の現実を知っていたからこそ、その現実を乗り越えようとして格闘したのであり、先の「先生」もまた、熱鉄を受けつけない人間の現実を知っていたからこそ、努力と英知によって、それを克服していく道を説こうとしていた。
それは「意のままにならない生」の現実に対する“熟慮”であって、現実の否定とは異なるのではないか、というようにである。
だがまさに、その点が違うのである。彼らは、「意のままにならない生」の現実から出発し、それを引き受けようとしたのではなく、あくまで現実の外側にある“理念”から出発していた。
「一切の犠牲を伴わない人間の生」や「一切の灼熱にも耐えうる人間の身体」などといった、現実からかけ離れた理想を起点として、そこから現実に立ち向かおうとしていたのである。
彼らは自らの現実に寄り添おうとする気も、その現実に込められた意味を理解しようとする気もさらさらない。そしてだからこそ、彼らは絶えず現実を否定し続けなければならなくなる。
「まだだめだ」、「まだ足りない」といって、いつまでも理想とは異なる現実を前に思い悩んでいなければならない。そしてついには、あるべき理想を実現できないからといって、自分自身を責めるようになるだろう。
「犠牲を伴わない生」が実現しないのも、「熱鉄に耐えうる身体」が実現しないのも、要はわれわれ人間自身、あるいは「この私」自身に原因があるのだ――「この私」(人類)が未熟であるから、「この私」(人類)が怠惰であるから、「この私」(人類)が愚かであるから、そして「この私」(人類)が根本的な欠陥を持つ存在であるからだ――といったようにである。
はたして読者には、この「若者」や「先生」の姿が滑稽に見えるだろうか。だが、これこそがわれわれ自身の姿なのである。思い返してみてほしい。われわれが「真の自由」、「真の平等」、「真の自律」、「真の共生」と口にするとき、その目線の先には何があったのだろうか。
集団に埋没することのない〈自立した個人〉でも、〈間柄〉なき〈関係性〉でも、負担なき〈共同〉でもかまわない。われわれはそこで、知らず知らずのうちに現実否定の理想を掲げ、あたかも先の「若者」や「先生」のごとく自ら“超人”になることを求めてきたのではなかっただろうか。
そしてこれらの「寓話」には、いずれも続きがあるのである。われわれ人間は、その驚くべき潜在力によって、「意のままにならない生」の現実を部分的には「意のままになる」ものへと改変することができるからである。
例えば高度バイオ技術を駆使することによって、微生物から完全食品を生みだすことに成功すれば、確かに先の「若者」は、「植物を犠牲にする」という自らの苦悩から解放される。また先の「先生」であれば、自分の右腕を切り落として、代わりに機械の腕をつなげばどうだろう。
なるほど、確かに熱鉄を持つことができるではないか。要するに、現実の外部にあったはずの理念が、ある面では実現してしまうのである。こうして彼らは、いつの日か本当に、自らがその約束の地へとたどり着けるような気がしてくる。
しかしそのことによって、かえって彼らは苦しめられるのである。夢が叶った「若者」は、今度は微生物を犠牲にすることに耐えられなくなる。機械の右腕を手に入れた「先生」は、今度は左腕が、あるいは脚が、熱鉄を受けつけないことに耐えられなくなるからである。
もう、これ以上繰り返す必要はあるまい。科学技術を搭載した〈社会的装置〉は、確かにわれわれを部分的には「意のままにならない生」から解放してくれる。
しかし逃れられると信じ込み、逃れようと足掻くほどに、理想と現実との間の亀裂は致命的に開いていくだろう。そして「意のままにならない生」の現実は、闇夜の月のごとくわれわれの後をついて回り、最後は容赦なくわれわれの前に君臨する(26)。
要するに〈自己完結社会〉に生きるわれわれの苦しみ、その根底にあるのは、〈無限の生〉が提示してきた人間的理想と、われわれが直面する人間的現実との間に生じたとてつもない乖離、両者の間でわれわれが引き裂かれていることにあるのである。
そして〈無限の生〉が敗北するとき、おそらくわれわれは、その迫り来る敗北感と自責の念とに耐えられない。「意のままになる生」こそが「正常」であると信じてきた人々は、そこで「意のままにならない生」とともに生きるということの意味、そしてそのための術というものを、何ひとつ獲得せずに生きてきたからである。
(4)究極の「ユートピア」――「脳人間」と「自殺の権利」 へ進む
【下巻】目次 へ戻る
(18)こうした整理に基づけば、【第九章】において見てきた「第二期」の戦後的理想、とりわけその中核をなしてきた「平和主義」と「民主主義」の理想が、いずれも「現実を否定する理想」としての側面を強く持っていたことが理解できるだろう。
(19)この論点をめぐっては、おそらく二つの留保が必要である。ひとつは、後の時代に理念がもたらした成功に見えるものであっても、実際には現実に基づく試行錯誤がもたらした成功に過ぎない場合があるということ、もうひとつは、理念の力が最も顕著に発揮された歴史的事例は、アメリカ独立戦争やフランス革命というよりむしろ、例えばカンボジアでポル・ポトが試みた実践などがそうである、ということである。このときカンボジアでは、都市を否定するところにある理想国家の建設のために、数100万人にものぼる人々が都市から農村へと強制的に移住させられた。驚くべきことに、その「社会実験」を通じて、最終的には全国民の1/4あまりが死亡したとされているのである。詳しくは山田(2004)。
(20)以下は、栗原敬遠が「郷土愛」という概念の無力さや虚構性について論じた一節である。「近代的自我の確立……それは同時に暗黒との戦いでもあった。選択行為が不可能な地点にあっては、私たちは何時までも自由を獲得できない。……しかし暗黒は消えなかった。暗黒は光のあるところに常に控えている。それはそもそも消えるの消えないのという次元で語る対象ではないのだ」(栗原 2016:106、傍点は筆者)。栗原が述べる「暗黒」とは、逃れられない人間の宿命、すなわち本書で〈有限の生〉と呼ぶものに相当する。またここでの「光」は、本書で言う無限の理想に相当する。この一文は、われわれが世界を〈無限の生〉の「世界観=人間観」のもとで眺めるとき、「意のままにならない生」の現実が、あたかも影のようにどこまでも追いかけてくる様子を鋭く表現しているのである。また増田敬祐は、この「無間地獄」について〈万能の否定論〉という概念を用いて説明している。「私たちの生きる現代社会は「人類史の構想」という発展進歩史観によって、生活の現実が常に「本来」の「あるべき姿」を前に、それが「前近代」であろうが、「未完の近代」であろうが、否定される方式となっている、ということである。この〈万能の否定論〉では、終着駅にたどり着いた=「本来」の「あるべき姿」に達したと認められない限り、現実の人間は何をしても「人類史の構想」を根拠に否定されてしまう」(増田 2020b:352)。
(21)われわれはこれまで一連の理念の先に、すべての人々が満たされ、光輝くような、どこかバラ色の世界をただただ素朴に信じてきたのではなかっただろうか。それがあまりに偶像化されていたので、おそらくわれわれは、こうした事実の側面をなかなか受け入れられずにいるのである。
(22)確かに自由も、平等も、自律も、共生も、社会的現実という次元においては、それらを必要としている人々が存在するだろう。その意味において、われわれは一部の国や一部の地域、一部の属性を持つ人々の間で自明視されている権利であっても、その恩恵を受けられない数々の人々が存在することを忘れるべきではないと言える。しかし本書が問題にしているのは、そうした社会的な不均衡のことではない。「存在論的自由」によって基礎づけられた理念の根底には、「無間地獄」が横たわっているということ、それらが「現実を否定する理想」として追求され続けたとき、人間の未来には何が待ち受けているのかということこそ、本書が問題にしていることだからである。
(23)ここでの根源的な「世界観=人間観」の変容のことを、吉田健彦は「デジタル化」と表現してきた。吉田の言う「デジタル化」とは、直接的には思考とデータが等価のものとして人々に認識されることを指している。しかしそれは科学技術の進展に伴って、第一に、異質なものとして現前する他者や、そうした他者との対峙によって立ち現れる「私」という存在を、操作可能なデータとして一元的に理解、置換できるものだと見なす「世界観=人間観」の成立として説明され(吉田 2017)、第二に、「存在論的ノイズ」のなかにおいてしか存在できない人間に対して、特定の人間像(人間類型)を「真の人間」と想定し、そこから外れるものをすべて「除去可能性ノイズ」という形で除去することが可能であり、また除去すべきだと見なす、「世界観=人間観」の成立として説明されている(吉田 2018)。歴史や記憶を含む「全体性」を纏い、絶対的に固有な存在として私に迫りくる他者は、ここではノイズを除去され、自意識を持て余す自身の自己確証のためのリソースとしてのみ理解されるようになる。そうして「他者原理」を喪失した「私」は、すべてがコントロール可能であるとする偽りの無限と永遠のなかで、孤絶した透明な存在になると説明されるのである。【第六章:注26】および【第八章:注64】も参照。
(24)栗原敬遠の「暗黒地域論」は、「地域起こし」や「郷土愛」の名のもとに称揚される「地域」なるものを紐解き、その根底にある矛盾や虚構性について論じたものである(栗原 2015)。栗原によれば、かつて「地域」を支えていたのは、「選択できない」ことを受け入れる世界観であり、そうした世界観を、当事者となる人々が了解、共有していたことであった。しかしそれは、今日では逆に「選択できる」ことを自明視するような世界観に置き換えられてしまっている。たとえ「選択できる」世界観のもとでどれだけ「地域」なるものを復元しようと試みても、人々はかえってその必然性に苦しむことになる。そして経済効果という理由を当てにした、まがい物ばかりを生産することにもなるだろう。結局そこには、根源的な持続性が欠落しているのである。この指摘は、本書で見てきた「世界観=人間観」の変容を別の角度から捉えたものだと言えるだろう。【注49】も参照。
(25)この「寓話」のなかの「殺生嫌いの若者」は、一見すると“ヴィーガン”と呼ばれる人々と重なる部分があるように思えるかもしれない。しかし本書がこの「寓話」を取りあげたのは、そうした人々の生き方を否定するためではまったくない。実際、第三者からヴィーガンとして認知される人々であっても、その信念の形はさまざまだろう。本書が批判しているのは、後に論じているように、あくまで自らの〈生〉の前提としてまぎれもなく殺生が君臨しているにもかかわらず、その現実を普遍的な「悪」(あるいは普遍的な「善」)として価値づけるような、「現実を否定する理想」に対してである。逆に言えば、たとえ「肉を食べない」という信念であっても、それが現実との格闘を通じて自身なりの“より良き〈生〉”として、すなわち「現実に寄り添う理想」として見いだされるということは十分にありえると言えるのである。
(26)例えば現代人が直面している“老い”の問題は、その典型的なものだと言えるのではないだろうか。実際、「かけがえのないこの私」を自明視してきた人々にとって、能力が衰え、外見が変わり、誰かの助けを必要とするようになる“老い”は、まさしく許しがたい不条理であるだろう。しかしこれまで見てきたように、そうした考えに至るのは、われわれ自身が人生の目的を「自己実現」と見なし、無意識のうちに特定の身体的状態のみを「正常」だと認識しているからではないだろうか(【注23】における吉田の「存在論的ノイズ」をめぐる考察も参照のこと)。われわれにとって、“老いる”ことはすでに身体の「非正常」であって、それは言ってみれば医学的に克服されるべき「疾患」のひとつとなっている。だが、どれほど金銭や労力を費やしたところで、われわれが“老い”から逃れることなど不可能であり、そこにあるのはまさしく先の「無間地獄」であるだろう。〈有限の生〉の「世界観=人間観」が訴えているのは、ここでわれわれが本当に必要としているのは、若返りの薬でも鋼鉄の身体でもなく、生老病死の全体としての〈生〉を見つめ、そうした〈生〉を引き受けていく意味であり、その過酷な現実と力強く対峙していくための術であるということなのである。〈有限の生〉を生きたかつての人々にとって、おそらく“老い”とは抵抗すべきものでも、克服すべきものでもなかった。彼らは、おそらく青年には青年の役割があり、老人には老人の役割があると考えていた。齢を重ねていくということは、人が人生に連なるひとつの舞台に別れを告げ、その都度別の新しい舞台に「誕生」するということを意味していたのである。