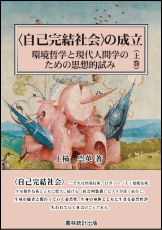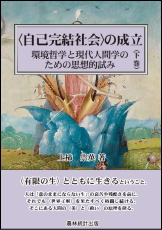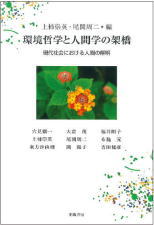『〈自己完結社会〉の成立』(下巻)
【第十章】最終考察――人間の未来と〈有限の生〉
(6)〈世界了解〉①――人間の〈救い〉について
〈有限の生〉とともに生きるということ――それが、本書が長い考察の末に到達した答えであった。
とはいえわれわれの議論には、おそらくまだ不足しているものがある。それは、〈有限の生〉とともに生きるための“術”に関わるもの、われわれが〈有限の生〉を肯定していくための、手がかりとなるものについてである。
ここでわれわれは、まず人間の〈救い〉というものについて考えてみよう(55)。
一般的な辞書によれば、“救い”とは「すくわれること、たすけること」、「加勢、助勢」、「希望や明るさを感じさせて気持をほっとさせることがら」などであるとされている(56)。しかしここで問題にしているのは、あくまで人生における〈救い〉、すなわち人間が生きることの〈救い〉についてである。
〈有限の生〉の内実を思えば、それが少なくとも「希望や明るさを感じさせて気持をほっとさせる」などと表現できるものではないということだけは分かるだろう。では、改めて人間の〈救い〉とは何だろうか。
このことを考えていくために、われわれはひとつの「寓話」から始めよう。
- あるところに、一代で巨大な帝国を築いた皇帝がいた。皇帝は富や権力をほしいままにしていたが、ただひとつだけ手に入らないものがあった。それは“永遠の命”である。年老いた皇帝は、滅びゆく自身の肉体を悲しみ、臣下に向かって“不老不死の薬”を探し求めるように命じた。ところが臣下はいつになっても戻らない。焦った皇帝は、伝え聞いた噂から、異国の神を祀れとあれば豪華な神殿を建造し、乙女の生き血が効くとあれば、国中から乙女を集めて首をはねた。そして毎日のように臣下の帰りはまだかと嘆き、暴れて回るために、周囲の人間たちからは「早く死んでくれたら」と影でささやかれながら、ついに息を引き取ったという――。
われわれはこれまで繰り返し、与えられた自身の〈生〉を全うすることの意義について論じてきた。その意味においては、確かに「皇帝」は、波乱に満ちた自らの〈生〉を全うしたと言えるだろう。
問題は、この「皇帝」の人生において、はたして人間の〈救い〉はあったのかということである。「皇帝」の事業は確かに偉大であった。それでも晩年において、彼の心は荒廃し、そこには一切の平穏がなかったと言える。
「皇帝」は、死すべき自身の運命を憎み、そうした運命を与えた天を憎み、そして自らを忌み嫌う周囲の人々を憎みながら死んでいった。そこにはおそらく、人間の〈救い〉はなかったのである。
だが、この「皇帝」の苦しみは、言ってみれば自縄自縛の苦しみではなかっただろうか。それは「意のままにならない生」の現実を否定し続けた、あの「皇帝」が自ら招いたものだったからである。
この「皇帝の寓話」は、なぜ〈無限の生〉というものが、人間の〈救い〉とは対極にあるものなのかということをわれわれに教えてくれる。
というのも、〈無限の生〉に囚われた人々の苦しみは――価値理念が実現しないからといって現実を否定し続けたあの理想家たちの苦しみから、「脳人間」に到来した、あの“退屈”という名の恐るべき虚無に至るまで――この「皇帝」と同じく、自縄自縛の苦しみだからである。
とはいえ、ある人々は次のように言うかもしれない。もしも人間の〈生〉が、根源的な部分で哀苦や残酷さに満ちているのだとすれば、われわれがたとえ〈有限の生〉を生きたところで、結局救われることなどないだろう。人間の〈救い〉など、結局どこにもないではないかというようにである。
確かにわれわれは、人間的な〈生〉の哀苦や残酷さからは決して逃れることができないと言える。しかし本書では、それでもなお、次のように主張したい。人生の〈救い〉というものがあるとするなら、それは依然として哀苦や残酷さを含んだ〈有限の生〉を肯定することそれ自体のなかにある、というようにである。
もっとも、このことを理解するためには、ここでの「肯定」が意味するものについて、われわれはより深く掘りさげていく必要があるだろう。
最初の手がかりとなるのは、かつてE・キューブラー=ロス(E. Kübler-Ross)が述べた、終末期患者が自らの現実を受け入れるまでにたどるとされる、「否認」(denial)、「怒り」(anger)、「取り引き」(bargaining)、「抑欝」(depression)、「受容」(acceptance)という五つの段階である(57)。
注目したいのは、このことが終末期患者に限らず、多かれ少なかれ、人々が「意のままにならない生」の現実に直面した際に示す、一般的な反応であると言えることである。
例えば不本意な〈生〉の現実と出会うとき、人々は最初、その現実がもたらした「裏切り」を受け入れることができない。しかしそれが間違いではないということが分かると、今度はそうした現実が自身に訪れたことに対して憤慨することになる。そして何かを代わりに差しだすことで、その現実を変更しようと試み、それがどうにもならないと悟って、ついには嘆きと悲しみに暮れるのである。
このとき、その人の苦しみの度合いは、その現実がその人の存在にとって重大な意味を持つものであるほど大きなものとなる。そして人々が、それを本来的に「意のままになる」べきものだと確信していたのだとするなら、その苦痛はよりいっそう大きなものとなるだろう。
しかしこの段階を乗り越えると、やがて怒りや抑鬱は背景へと退いていく。そして人々はあるがままの現実を、あるがままのものとして受け入れるようになるのである(58)。
こうしたある種の段階は、おそらく〈有限の生〉の「肯定」についてもあてはまる部分があるだろう。しかし問題となるのは、この「あるがままのものとして受け入れる」ということに含まれている、より根源的な何かである。
そしてその手がかりとなるのは、われわれが【序論】で述べた、人間的世界における〈思想〉の存在理由、すなわち人間存在は、根源的に世界を了解し、他者を了解するための意味と言葉を必要としているという前提である。
前述したように、人間はその存在の始原において、根源的に不可解で「意のままにならない」世界に投げだされ、同時にそこで、同じように不可解で「意のままにならない」他者とともに生きていくことを余儀なくされる。
ここで人々が求めているのは、そうした自身を取り囲んでいる、「意のままにならない身体」をも含んだ物質的な世界への了解とともに、「意のままにならない他者」との〈関係性〉をも含んだ、非物質的な世界への了解であると言えるだろう。
本書では、それらを包含する形で〈世界了解〉と呼ぶことにしたい。すなわち〈世界了解〉とは、他者を含んだ「意のままにならない」この世界そのものに対して、あるがままのものを、あるがままのものとして一度は受け入れるという意思のあり方のことである。
つまり〈有限の生〉を「肯定」するということは、突き詰めて言うなら、ひとりの人間存在が、こうした根源的な人間の宿命を受け入れていくこと、この〈世界了解〉を成し遂げていくということを意味しているのである。
したがって、ここでわれわれに残された問いは、次の二つとなるだろう。
ひとつは、現代を生きるわれわれが、いかにしてこの根源的な〈世界了解〉を達成することができるのかということ、もうひとつは、この〈世界了解〉を実現することが、なぜ人間の〈救い〉と結びつくのかということである。
ここでわれわれは、例えば古に生きた人々が、なぜ何ものかを神と呼び、この世界に人智を超えたよろずの物事を見いだしてきたのかということを思いだしてみる必要がある(59)。それは彼らが、いわばそうしたものを仲立ちとして、この〈世界了解〉を成し遂げようとしてきたからではなかっただろうか。
つまり人間存在が生みだしてきた多くの言葉、多くの意味は、より良き〈生〉を生きるための知恵であると同時に、〈世界了解〉を達成していくための知恵でもあったのである。
確かに現代を生きるわれわれの目には、もう古の人々には見えていた、あの人智を超えたよろずの物事は映らないのかもしれない。しかしわれわれにあっても、〈世界了解〉を促し、それを支えていく術は確かに残されているはずなのである。
おそらく〈世界了解〉の出発点となるのは、まずはその人自身が、この世界の現実に一歩踏みだしていくことであるだろう(60)。〈世界了解〉は、たとえそれが不完全なものであっても、その人が現実と対峙しようと試みるならば、その格闘の事実によって支えられるからである。
価値理念を盾に、闇雲に現実に立ち向かうわけでもなく、また卑屈な「諦め」によって、現実を蔑ろにするわけでもない(61)。何かに負い目や引け目を感じようとも、移りゆくこの世界の片隅で「意のままにならない生」を生き抜こうとする構え方、それ自体がその人を強くするからである(62)。
われわれは先に、人生が有限であるからこそ、そこには生きる意味が生じてくるのだと述べた。そのことが示唆しているのは、真に人を動かす意味があるとするなら、それは何ものかによって与えられるものでも、論証によって解明されるものでもない、現実との格闘のなかで、本質的におのれ自身が見いだすべきものであるということである。
次に〈世界了解〉を支える第二のもの、それはおそらく同じ世界と向き合う“他者”の存在である。
もっともそれは、親密な何ものかによる「この私」への無条件の承認などといったものではないだろう(63)。現代人が逃げ込む「自分だけの世界」は、「かけがえのないこの私」の聖域であると同時に、自縄自縛の牢獄でもある。それを打ち破る力になるのは、「意のままになる他者」ではなく、あくまで「意のままにならない他者」の存在だからである。
「不介入」に慣れてしまったわれわれの目には、そうした他者が、ときに「この私」を針で傷つけ、笑いながら足蹴にしてくる怪物のように映るかもしれない。それでもその人が、負担を伴う〈共同〉を引き受け、そのなかで〈役割〉や〈信頼〉や〈許し〉の経験を積み重ねていくことができるのならば、その経験によって、おそらくその人は強くなる。
大事なことは、人が何かを背負おうとするからこそ、〈役割〉は意味を持つのだということ、〈間柄〉を引き受けつつも、人が「〈我‐汝〉の関係性」として向き合おうとするからこそ、そこには〈信頼〉が育っていくのだということ、そして人が誰かを〈許そう〉とするからこそ、やがてはその人自身もまた〈許される〉のだということである。
移りゆく世界のなかで、それらは確かに永続的なものではないかもしれない。「素朴な〈悪〉」や人心の巡り合わせによって、そのすべてが成功するわけでもないだろう。しかし、そうした変わりゆくものを見守っていく姿勢もまた、おそらく〈世界了解〉の一部なのである。
そしてだからこそ、われわれは思うべきだろう。たとえ何かが終わりを迎えようとも、たったひとときであれ、そこにかけがえのないものがあったとするなら、それは偽りではなく、おのれだけのささやかな真実であると。
こうしてわれわれは、再び〈存在の連なり〉に思いを馳せることになる。〈世界了解〉を支える第三のもの、それはこれまで生きて死んでいった無数の人々の〈生〉、そしてこれから生きることになるだろう無数の人々の〈生〉のなかに位置づく、〈自己存在〉というものへの深い理解だからである。
このことを考える手がかりとなるのは、人間存在における“死”とは何かという問題である。
例えば〈無限の生〉の住人たちは、いまでも快楽を貪り、偏狭な自己を実現していくことだけが生きる意味であると考えている。そうした人々にとって、苦しみに満ちた〈生〉など、そもそも生きるに値しないもの、そして“私の死”とは、「かけがえのないこの私」が終焉を迎えるという意味において、絶対的な不幸となるだろう。
だが、人間存在にとっての“死”とは、はじめからそのようなものとして理解されるものだったのだろうか。はたして本当に、誰もがあの「皇帝」のように、不死を願って生きてきたなどと言えるのだろうか(64)。
例えば近代的な医療が普及する以前の時代、栄養失調や伝染病、事故や天災などによって人間は簡単に死に至った。十分な健康と安全が得られないなかで、悲惨な光景が至る所に見受けられた。
そうした世界にあって、人々が生きようとしたのは、損得勘定によって「苦しみよりも快楽が勝った」からだったのだろうか。あるいは彼らが心から「生きたい」と自己決定したからだったのだろうか。
そうではあるまい。人が生きたのは、むしろ「生きなければならなかった」から、つまり自らの意思とは関係なく、「この世に生まれてしまった」からではなかっただろうか。人は「生まれてしまった」以上、そう簡単に死ぬことなどできなかった。
例えば人間は、この世界に誕生したそのときから、有限な存在としての何ものかを背負うことになる。「意のままにならない身体」を背負い、同時に「意のままにならない他者」との〈関係性〉を背負うことになる。そして否応なく、あの〈存在の連なり〉のなかに位置づけられ、さまざまな縁のもと、自らが負うべきものたちと出会ってしまうのである。
だからこそ、おそらく人は死ぬことができなかった。生きようとして、格闘しなければならなかった。だがいずれは運命が、その人に有無を言わさず死を与える。それは、〈連なり〉のなかで生かされていく人間が、同時に有限な存在としての負うべきものを全うし、その責務からついに解放されるということをも意味していたのである。
それゆえ、人間が生きることを「この私」が生きることだと履き違え、限りあるものを偽りの永遠によって糊塗しようとする人々には、繰り返し死者のための墓標を立て、葬儀を営んできた人々の、そして行き倒れた見ず知らずの人間でさえ弔おうとしてきた人々の思いなど知るよしもないだろう(65)。
われわれはここで思いだすべきである。人間が「〈生〉の舞台装置」としての〈社会〉を生みだして以来、われわれの〈生〉は〈社会〉を介して途切れることなく続いていくものとなった。そのとき人間的な〈生〉は、「この私」という個体によって根源的に完結しないもの、〈存在の連なり〉の網の目のなかで立ち現れてくる〈この私〉として生きることを意味するようになったのである。
だからこそ人間存在にとっての死は、一般的な生物存在とはまったく異質のものとなる。人間的世界においては、たとえ肉体が滅びようと、たとえその人の記憶が忘れ去られようと、その人が生きて何かに働きかけた事実の痕跡、あるいはその人が創出した意味や言葉の痕跡は、〈連なり〉の片隅に確かに刻まれ、〈連なり〉のなかに永劫残されていくことになるからである(66)。
実際、われわれを取り囲んでいる「社会的なもの」とは、まさにそうした幾百億もの過去の人々が生と死を介して刻んできた痕跡そのものではないか。
だが、これは同時に恐ろしいことでもあるだろう。なぜなら〈存在の連なり〉を生きるということは、たとえわれわれがいかなる生き方を選択しようと、その生きた痕跡が否応なく世界に刻まれてしまうということをも意味しているからである。
このことを思えば、自意識に彩られた「この私」や「自分だけの世界」というものが、いかに狭小なものであるのかが分かるだろう。
はたしてわれわれは、その〈自己存在〉の始原にあって、同時にその先へと続いていくもの、原始より途切れることなく続いてきたその果てしない営為を〈信頼〉することができるだろうか(67)。
人が生きることの哀苦や残酷さを前にして、これまで生きて死んでいった無数の人々の〈生〉、そしてこの世界でこれから生きていくはずの無数の人々の〈生〉を、〈信頼〉することができるだろうか。
〈存在の連なり〉を生きる〈この私〉というものを覚悟するとき、はじめてわれわれは、真に「担い手としての生」を生きられるようになる。そこにある「人間という存在に対する〈信頼〉」、それが〈世界了解〉を成し遂げようとする人たちの心を勇気づけるからである。
そしてこのことは、人生の〈救い〉というものが、なぜ〈有限の生〉の肯定と〈世界了解〉のなかにこそあると言えるのか、ということをわれわれに教えてくれる。なぜなら、この〈世界了解〉へと至る道の先にこそ、おそらく「自己への〈信頼〉」と呼べるものが存在するからである(68)。
われわれが必要としているのは、「かけがえのないこの私」を肯定することでも、偏狭な自意識を誰かにありのまま受け止めてもらうことでもない。
求められているのは、人間が生きることの哀苦や残酷さを前に、なお現実と対峙していくことができる、人間としての自信だからである。それは、他者とともに〈生〉を実現していく主体としての自信、困難を前にして自分自身に大丈夫だと言ってあげられる心の強さだからである。
それらを支えてくれるのは、この世界に一歩踏みだしていく勇気と、〈共同〉を通じて積み重ねられた〈役割〉や〈信頼〉や〈許し〉の経験、そして〈存在の連なり〉のなかで「担い手としての生」を生きる覚悟とによって形となった、〈自己存在〉に対する自分自身の〈信頼〉に他ならない。
それゆえ、本書では改めて主張しよう。この時代に生きる、人間存在の〈救い〉とは何だろうか。それは〈世界了解〉を達成しようと格闘するなかで、「自己への〈信頼〉」へと至ること、そしておのれに与えられた〈有限の生〉を引き受け、運命が解放するその日まで、それを全うしていくということに他ならないと。
(7)〈世界了解〉②――人間の〈美〉について へ進む
【下巻】目次 へ戻る
(55)この人間の〈救い〉という主題は、これまで人文科学が十分に向き合ってこなかった主題であるように思える。それはおそらくこの主題が、もっぱら宗教の課題として理解されてきたこと、あるいはこの主題に相当する問題が、「かけがえのないこの私」や「自己実現」の問題として置き換えられて理解されてきた側面があったからである。しかし本書で見ていくように、〈救い〉を問題にすることは、〈思想〉の実践を行うにあたって本来避けて通ることができないものである。もっとも、〈思想〉の実践における〈救い〉の問題を、「こうすれば救われる」という具体的な実践内容の提示を意味するものだと誤解してはならない。その目的は、あくまで人間存在にとっての〈救い〉の意味、現代を生きる人々にとっての〈救い〉の意味それ自体を言葉によって紐解いていくことにあるからである。
(56)『広辞苑』(2018)には「①すくうこと。たすけること。救助。救済。②兵を出して救うこと。加勢。助勢。③希望や明るさを感じさせて気持をほっとさせることがら。④キリスト教で、イエス=キリストの救済。」とある。
(57)キューブラー=ロスは、「受容」の段階について次のように述べている。「かれは自分の“運命”について抑欝もなく怒りも覚えないある段階に達する。……かれは自分をとりまく多くの意味深い人々や場所などを、もうすぐすべて失わなければならないという、その嘆きも悲しみも仕終え、かれはいまある程度静かな期待をもって、近づく自分の終焉を見詰めることができる」(キューブラー=ロス 1971:146、Kübler-Ross 2014:109)。
(58)この過程は、【第九章:注101】で触れた芹沢(1989)が、「イノセンスの解体」と呼んだものとも密接に関わるものだろう。芹沢はそれを子どもたちの文脈において論じたが、それを必要としているのは、実際には子どもたちだけではない。人間存在が生きることそのものが、根源的に「イノセンスの解体」を必要としていると言えるのである。
(59)大野晋(2013)は、古来より日本語で「神(カミ)」と呼ばれてきたものの特性を、以下の六つにまとめている。①カミは唯一の存在ではなく、多数存在した。②カミは具体的な姿・形を持たない。③カミは漂動・彷徨し、時に来臨し、カミガカリする。④カミはそれぞれの場所や物・事柄を領有し支配する主体である。⑤カミは超人的な威力を持つ恐ろしい存在である。⑥カミは人格化してふるまう。例えば、祖霊につながる氏神にはじまり、土地の神である産土神や、自然の力を体現した火の神、水の神、それどころか山の神、道の神、坂の神、屋敷の神に至るまで、この列島に生きた人々は、〈生活世界〉の実にあらゆるところに「神」の存在を見ていた。それは一神教における神(God)とはまったく異質の概念であって、そこでは得体の知れない魑魅魍魎を含めて、人知を超えた畏怖すべき存在はすべて「神」なのであった。確かに現代の世界観からすれば、こうした存在は古代の人々の想像物に過ぎないということになる。しかしそれだけでは、あまりに表面的な理解にとどまるだろう。ここで重要なことは、人々がそうした存在を仲立ちにして、何を見ていたのか、何と向き合い、何を成そうとしていたのかということである。岡田編(2010)、小松編(2011)も参照のこと。
(60)増田敬祐は、人間存在が「自身の環境の外部に出る」ということの意味を、“環境”、“存在”、“倫理”の関係性を念頭に次のように述べている。「境界の発生は自分と自分以外の何ものかの〈間〉における触れ合い、関わり合うという空間に現われる出来事の発現でもあった。従って環境の了解は同時に自分という存在の縁取りを承知することで自分以外の人間存在を発見し、お互いが生存することを維持していくために行為する存在としての人間を了解する経験ともなる。……存在する「もの」どもは、生存のために環境世界に出る。そのとき行われる行為や活動は必ず自分以外の何ものか、他者との関わり合いを影のように連れ合っている。……本論は時代や環境を生き抜くために必要とされる倫理や作法の導出は、個人の人格を高めるという自己の内面性の陶冶に注目する仕方ではなく、存在する「こと」のために人間が自分の環境の外に出ていく渦中で取り結ばれる「人間どうしの間でかわされる結合的な行為」において体得されるものだと考える」(増田 2017:257-258、268)。
(61)この二つの態度は、実は根底においては深く結びついている。本来“諦め”は、現実肯定とも結びつく態度であると言えるのだが、少なくとも【第九章】で見てきた「第四期」以降に特有の「諦め」は、「意のままになる生」の歪んだ理想がもたらした挫折に起因するものであり、その意味において両者の出発点は同じものだからである。先のキューブラー=ロスの概念に引きつけて言えば、無限の理想を追い求める人々の態度は、「怒り」や「取引」に近く、「諦め」に陥った人々の態度は、「抑鬱」に近い。両者はいずれも「意のままにならない生」を結局は否定しているのであり、ここにあるのは、生身の〈生〉の現実を肯定できないことへの苦しみなのである。
(62)ここでの「構え方」という言葉は、バンド“北南”の楽曲『構え方』(『福がくる』収録、尻目庵、2009)から触発されたものである。
(63)このことを強調するのは、前述した芹沢(1989)をはじめ、80年代以降の多くの論者たちが、われわれの苦しみの根源を「存在論的抑圧」にあると考え、たった一人でも「ありのままの私」を受け入れ、肯定してくれる人間が必要であると主張してきた側面があるからである。しかし繰り返すように、一切の抑圧的、権力的な要素の介在しない〈関係性〉など存在しないし、〈関係性〉から切り離された「ありのままの私」など虚構の産物でしかない。無条件の承認を必要としているのは、あくまで幼児期の子どもたちであって、人々が本当に必要としているのは、おそらく「意のままにならない他者」と向き合い、互いに努力を重ねるなかで築き上げられていった〈信頼〉の経験だと言えるだろう。
(64)確かに歴史を紐解いていけば、「皇帝」のような人物はいつの時代も存在したと言える。例えばそれは、能力は高いものの、派手を好み、どこか独りよがりな一面をも兼ね備えた権力者だったのかもしれない。そうした人々は、生老病死を受け入れられず、「意のままになる生」の夢想に縋り、せめて自身の記憶が人々から失われないようにと、躍起になって「この私の生きた証」を残そうとする。しかしそれは、「意のままになる生」の夢想に浸れるだけの“余裕”のある人々の発想であって、一般庶民の感覚とはかけ離れたものだったのではないだろうか。
(65)一般的に墓や葬儀は、死者のために存在するものだと思われている。実際〈無限の生〉の住人たちにとっては、それらはあの「皇帝」と同じように、「この私が生きた証」を表現するものでしかないだろう。だが、はたしてそれだけなのだろうか。例えば人が誰かを弔おうとするとき、そこにあるのは、死者への同情だけではないだろう。この列島においては、古くから非業の死を遂げた人間の霊魂が、何らかの怨みや邪念を抱いて災難や祟りを引き起こすと信じられてきた。人々が死者を丁重に弔ったのは、一面においてはこうした「鎮魂」という意味合いも含まれていたのである。そして死霊を恐れる人々の心のなかには、自らが生きることへのさまざまな「負い目」もまた含まれていた。「人の死」と向き合うということは、故人と縁を結んだ人々が、それぞれの形で自身の「負い目」と向き合うこと、そして人々が故人と縁を持つ別の誰かと何かを分けあうことによって、同時におのれ自身の〈生〉と向き合うという側面があったのである。その意味においては、葬儀も、墓も、実は生者のためにこそ存在してきたとも言える。それらは〈存在の連なり〉のなかで生きなければならない人間が、自分自身を再確認するためのものでもあったのである。日本古来の弔いの思想については、川村(2015)、相良(1990)を参照のこと。
(66)例えば想像してみてほしい。あなたが友人に対して何の気なしに口にした言葉があったとして、その後友人とは疎遠になってしまったものの、後になって、その人が人生の岐路に直面した際、不意にその言葉を思いだして、それをきっかけに危機を克服することができたとする。その人はすでに、あなたのことは忘れてしまっていたが、その言葉だけは生きていて、それはその人のなかで磨かれていき、いつしかその人自身の言葉になっているかもしれない。そして今度は、その人が語りかけたその人自身の言葉によって、また別の誰かが結果的に救われることになるかもしれない――人間の世界においては、こうしたことが実際に起こりえるのである。本書で述べる〈存在の連なり〉をめぐる感覚は、筆者だけのものではないだろう。例えば魚戸おさむ/北原雅紀(脚本)の漫画作品『玄米せんせいの弁当箱』には、次のような台詞が登場する。「三つ目の命は死なないんです。……一つ目の命は“人生”、二つ目の命が“思い出”、三つ目の命は――“魂”です」(魚戸/北原 2008:139)。
(67)このことと関連するものとして、吉田健彦は次のように述べている。「我々が共同について語れるのだとすれば、それは他者の他者原理という語義上の不可能性を超えた信頼によるより他はない。そしてそうであるのなら、このとき信頼は、普遍的な善性や共感への安直な妄信を意味しているのではなく、むしろ、互いが互いにとって恐怖と苦痛でしかなく、にもかかわらず、あるいはその恐怖と苦痛故にこそ、無数の貫通がこの私を私たちへとつなぎとめることへの確信を意味している。言い換えれば、それはこの私の他者原理において貫通が顕現する際の確かな手触り、つまり存在論的ノイズという否定しがたく生々しい摩擦への観取の実感であり、その摩擦こそが跳躍への踏み切りをもたらすのだ」(吉田 2018:264-265)。
(68)筆者は、それを敢えて「自己肯定」と呼ぶことを避けた。というのも、現代人が「自己肯定」と言ってしまうと、それは容易に「かけがえのないこの私」の概念と接続され、世界も他者も欠落した、肥大化した自意識の肯定へと向かってしまうおそれがあるからである。先の「皇帝」だろうと、自死した「脳人間」だろうと、自意識自体の肯定はできる。人間の〈生〉の残酷さを思うとき、「この私でよかった」、「生きていてよかった」、「生まれてきてよかった」といった言葉は、あまりに虚しく響くだろう。人間の〈救い〉となるものの契機は、あくまで〈世界了解〉にある。したがって「自己肯定」というものがあるのだとすれば、それは〈世界了解〉を土台とした「自己への〈信頼〉」がもたらす、あくまで副産物であると考えるべきだろう。