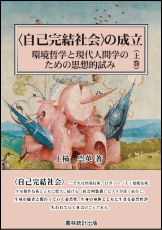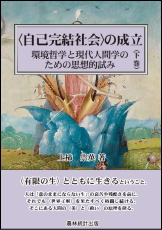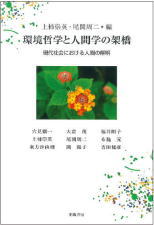『〈自己完結社会〉の成立』(下巻)
【第十章】最終考察――人間の未来と〈有限の生〉
(7)〈世界了解〉②――人間の〈美〉について
最後にわれわれが見ていくのは、人間存在にとっての“美”の問題についてである(69)。
長い議論の果てに、なぜわれわれは美について論じなければならないのだろうか。それは「美しく生きる」ということが、〈有限の生〉とともに生きる術、われわれがより良き〈生〉を模索していくための、ひとつの手がかりとなるからである。
したがって、ここで考察したい〈美〉とは、例えばわれわれが何かの情景や芸術(作品)を捉えて「美しい」と感じるような、「鑑賞としての美」のことではない。
ここでの〈美〉とは、もっぱら人間存在を対象とし、ある人々の〈生〉のあり方、あるいは自らの生き方をもって「美しさ」を論じる目なざしのことを指している。本書ではそのことを、「生き方としての美」と呼ぶことにしよう。
もっとも、こうした〈美〉の内実について踏み込んでいく前に、われわれは美というものをめぐる、一般的な議論について確認しておく必要があるだろう。
というのも、現代社会の美的状況においては、美とはもっぱら「鑑賞としての美」のことを指し、「生き方としての美」については、およそ美の問題とは見なされていないということ、他方で「現代アート」(contemporary art)の氾濫によって、これまで美を独占してきたはずの芸術領域においてでさえ、「美そのもの」が解体され、われわれはある種の「美的アノミー」とも呼べる事態に陥っているように見えるからである。
実は歴史を遡れば、「生き方としての美」という概念は、近代以前の思想においては、広く一般的に見られるものであった。それは伝統的に“美徳”と呼ばれる範疇であり、儒教世界から古代ギリシャに至るまで、あらゆる文化圏において独自の形で成立してきたものだと言えるだろう(70)。
大きな転機となったのは、18世紀の西洋世界において、芸術=美=感性を三位一体とするような西洋美学(aesthetics)が成立し、同時に哲学思想上の枠組みのなかで、道徳(善)と美が区別されるようになったことである(71)。
西洋美学においては、美は、優美や崇高といった“美的範疇”に属する普遍的価値であると見なされ、それを喚起させるものこそが芸術(作品)であると考えられた。またそうした美は、知性や論理ではなく、感性によって理解されるとされ、ここから芸術(作品)を通じて普遍的な美そのものを感性的に掌握していく“美的体験”という主題が形成されていく。
他方で、人間の生き方を論じることは、もっぱら倫理学や政治学の関心事項となり、次第に美との接点を失っていった。こうして美の舞台は、およそ芸術(作品)やそれに準ずるものへの鑑賞活動へと収斂していき、「鑑賞としての美」こそが美学の標準となっていったのである。
ただし、こうした美学の枠組みは、20世紀においてさらに変容していくことになる。それはM・デュシャン(M. Duchamp)に始まる「現代アート(72)」の成立によって、芸術(作品)の役割が、単純に美を表現するものではなくなっていったからである(73)。
例えば今日「アート」と言えば、既成概念を破壊すること、新たな感覚世界を提示すること、さまざまな連想を喚起させること、さらにはそれらを通じて、政治的主題をも含む形でわれわれ自身を省みる仕掛けを提示することなど、そこでは実に多様な役割が想定されている(74)。
また芸術(作品)の様式においても、観衆が身体を用いて干渉する、美術館を飛びだす、果ては料理を振る舞って一緒に食べるなどといったように、さまざまなものが存在すると言えるだろう(75)。
注意を必要とするのは、こうした潮流が、必ずしも「鑑賞としての美」の独占的地位そのものを破壊したわけではないということである。
例えば「現代アート」は多様な解釈を受けつけるものの、作品を作品ならしめているのは、あくまで知的に理解されうる「コンセプト(美的概念)」の存在である。換言すると、ここでは作品自体が、常に解説を通じて特定の意味の文脈に接続されていなければならない。
このことは観衆の側から見れば、それがいかに奇抜な様式だろうと、そこでの体験は、依然として「コンセプト」に沿ったある種の「鑑賞」活動であるということになるからである(76)。
「現代アート」が破壊したのは、むしろ美に対する姿勢の方であった。そこでは、既成概念の破壊がまさに「美そのもの」に対して向けられたために、結果として、「コンセプト」や解釈さえ成立すれば、あらゆるものが潜在的な芸術(作品)となりうる事態となった(77)。
それは言ってみれば、「美的なるもの」が醜悪なものや残忍なものさえ含んだ万物にまで無制限に拡張されていく事態、あるいは「美そのもの」が跡形もなく融解し、あたかも芸術(作品)が「美そのもの」から離脱したかのように見える事態だったのである(78)。
「現代アート」はこうした構造ゆえに、ますます「コンセプト」に依存し、インパクトばかりを追求するようになっていく。そしてその結果として、芸術(作品)はますます即物的で、観念的、そして直情的な趣向を帯びるようになっていくのである(79)。
したがって今日のわれわれが、無数の「美的なるもの」に取り囲まれていながら、「美そのもの」においてはしばしば恐ろしく空虚に見えるとするなら、それはこうした「鑑賞としての美」の寡占状態と、「アート」の異常な氾濫によって、われわれがある種の「美的アノミー」へと陥っているからだと言えるだろう。
しかし美とは本来、人を動かす力を秘めたものであった。そしてそれは、人々が作品の奇抜さによって圧倒されるからでも、「コンセプト」の真新しさによって知的に興奮するからでもなかったはずである。
われわれはここで、原始以来、なぜ人間存在は芸術というものを創出してきたのか、そして美というものを通じて、人々が何を託そうとしてきたのかということについて考えてみる必要がある。
手がかりとなるのは、われわれが【序論】で触れたように、芸術活動に潜在している哲学や宗教との共通点である。そしてそれは、これらがいずれも何らかの〈思想〉を表現したものであるということであった。つまり芸術もまた、その根源において「意のままにならない生」を生きる、人間存在の〈世界了解〉と結びついているのである。
例えば誰ひとりとして理解者がいないままに、ひとつの造形をひたすら追い求めた彫刻家だろうと、たったひとつの瞬間を描くためだけに、完璧な物語を創りあげていった小説家だろうと、おそらくそこには芸術家にしか成しえない現実との格闘があった。それは、「意のままにならない生」を生きなければならないひとりの人間の、言ってみれば〈世界了解〉の表現なのである。
そもそも人はなぜ、芸術(作品)に触れて心が揺り動かされるのだろうか。それは芸術(作品)というものが、ひとりひとりの美意識に訴えかける何かを秘めているからである。
では、“美意識”とは何だろうか(80)。それは突き詰めて言えば、その人自身の生き方そのものであると言える。それは「意のままにならない他者」や「意のままにならない身体」、そしてこの「意のままにならない世界」において、より良き〈生〉を求めて生きようとする、その人自身の構え方だからである。
人が芸術(作品)に感動するのは、そこにそれぞれの時代、それぞれの境遇を生きたひとりの人間にとっての、〈世界了解〉を成し遂げていく人間的な強さ、〈世界了解〉を果たしえない人間的な苦しみ、あるいは「美しく生きたい」というその人自身の願いが表現されているからに他ならない。
われわれが忘れていたのは、「鑑賞としての美」の背後にあるべき美意識の問題であって、それは何よりこうした「生き方としての美」を問題にするということを意味しているのである。
われわれはここで、ようやく当初の問題意識に立ち返ることができるだろう。それは〈有限の生〉を生きようとする人々にとって、この「生き方としての美」に根ざした美意識こそが、より良き〈生〉を全うしていくひとつの指針となるということである。
例えば「生き方としての美」とは、言い換えれば「美しく生きる」ということでもあるだろう。われわれ人間には、自らの行いがはたして「美しい」ものだったのかと問い続ける力がある。その感情に訴えかけるものこそ、ここで人間の〈美〉と呼んでいるものの本質なのである。
「生き方としての美」を考えるうえで、最初の要件となるのは、それが普遍的な道徳原理から導かれるわけでも、社会的に合意された価値規範から導かれるわけでもないということである。
万人にとっての普遍的な美など、おそらく〈無限の生〉の理想家たちの夢のなかだけの産物に過ぎない。また人間的な世界においては、「美しく生きよう」とするからこそ、社会的な価値規範から逸脱しなければならないときがあるだろう(81)。
人間の「生き方」の美しさに、絶対的なものなど存在しない。それはあらゆる〈思想〉がそうであるように、〈世界了解〉に臨む人々が、本質的におのれの力で見いだしていくべきものだからである。あるいは無数の試みが誕生しては消えて行く人間存在の営みそのものを肯定し、また時代に生かされていく自らの不完全さを覚悟しながら、それでもおのれが信じた道を行くべきものだからである。
われわれが同じ世界の現実と対峙している以上、その人が見いだした〈美〉の理解者は必ずどこかに存在する。また、たとえ命あるうちにそうした人間と出会うことができなくとも、いつの日かその人と同じ感情を背負うだろう人間が必ずどこかに生まれてくる。それはちょうど、その人が500年前の名もなき詩人の言葉にさえ美意識を揺り動かされてきたのと同じように。
そのことを〈信頼〉しつつ、自らの思う「生き方としての美」を全うしようと格闘すること、ここにこそ、おそらく人が〈美〉を希求しながら生きるということの最も純粋な形があると言えるのである。
とはいえわれわれは、全員が「芸術家」であるわけではないだろう。また「生き方としての美」に投身していくことだけが、必ずしも「担い手としての生」を生きることのすべてではない(82)。それでも〈有限の生〉とともに生きる人々にとって、人間の〈美〉は、確かにより良き〈生〉のための手がかりをわれわれに与えてくれる。
例えば「美しく生きる」ということは、「誇り高く生きる」ということでもあるだろう。「意のままにならない生」を生きるとき、人は誰しも逃れられない何かを背負い、ときに望まぬ何かを引き受けなければならない。そうした人生の宿命を前にするとき、無限の理想や価値理念など、まるで紙屑のように消し飛んでしまう。そうしたなかでも、はたして“誇り”を失わずに生きていけるのか。
美意識が問われてくるのは、まさにそうした瞬間である。美意識を失った人間は、そこで卑屈になるより他はない。よこしまな情念を膨らませ、いやだいやだと誰かを憎んで生きるしかない。しかしいかなる状況においても、より良く生きるための手立ては必ずどこかに残されている。そこで人が現実との格闘を投げだすことなく、踏みとどまっていられるとしたら、そうさせるのは、その人自身の人生に対する“誇り”なのである。
また「美しく生きる」とは、「誠実に生きる」ということでもあるだろう。「誠実に生きる」とは、まずもって自らが与えられた「担い手としての生」を精一杯生き抜いていくことを意味している。
だがそれは、口で言うほど容易なことではない。「意のままにならない生」の現実は、より良く生きようとする人々のささやかな祈り、ささやかな願いさえも簡単に突き崩してしまうからである。
人生には、信じてきたもの、頼りにしてきたものが無残に崩れ落ちていく瞬間がある。あるいは時の奇妙な巡り合わせが、刹那にその人の感情や行動を狂わせ、すべてを台無しにしてしまうことさえあるだろう。そうしたとき、人は誇りを失ってしまう。自らの〈生〉が空虚なもの、無意味なもの、汚れたものだと感じてしまう。
だが、そのように思う必要などない。われわれに〈連なる〉幾千億もの〈生〉のなかで、挫折を経験しなかった人間、何かを誤らなかった人間などひとりも存在してこなかったし、これからも決して存在することはないからである。
その人のなかに美意識が残されているなら、その人は苦境においてもなお呼びかけられているはずである。「誠実に生きよ」と。
挫折や誤りそのものよりも、そうした現実の先にどう生きるのかということこそが、その人自身の人生に対する“誠実さ”を決定する。人には誰しも縁によって出会い、「意味のある〈関係性〉」を築いてきた何ものかが存在するだろう。そしてその先には、自身に〈連なる〉過去に生きただろう人々、そして未来に生きるだろう無数の人々がいる。
「誠実に生きる」ということは、そうした人々のことを思い、彼らに恥じない生き方を、そして少しでも誇れる生き方を選択しようとすることなのである(83)。
いずれにしても、われわれがより良き〈生〉を求めるならば、われわれ自身が「生き方としての美」に宿る美意識を鍛錬していく必要があるだろう。
例えばわれわれは、あの〈存在の連なり〉そのものを「美しい」と思えるだろうか。そこには、人間存在が生きることの哀しみも、苦しみも、無力さも、残酷さも、そのすべてがあると言えるだろう。しかしそこに「美しさ」があるとするなら、それはおそらく人間存在の「美しさ」、あるいは人生そのものの「美しさ」と同じものであるはずである。
はたしてわれわれは、その「美しさ」を〈信頼〉できるだろうか。だが、そうした問いのなかにこそ、より良き〈生〉を生きるための確かな手触りがあるのである。
(8) 結論 へ進む
【下巻】目次 へ戻る
(69)一般的な辞書によると、“美”とは、第一に「うつくしいこと」、第二に「よいこと。りっぱなこと」、そして第三に、哲学的な用法として「知覚・感覚・情感を刺激して内的快感をひきおこすもの」でありながら、「生理的・個人的・偶然的・主観的」である「快」とは対照的に、「個人的利害関心から一応解放され、より普遍的・必然的・客観的・社会的」なものであるとされている(『広辞苑』 2018)。
(70)例えば孔子の教えは、君主や父子、兄弟など、人間存在がさまざまな立場のなかで「良く生きる」ことを問題としていたし(金谷 1999)、古代ギリシャで言えば、アリストテレスが倫理学の主題とした「卓越性(arete)」もまた、人間が「良く(善く)生きる」ことを問題とする概念であった(アリストテレス 1971)。重要なことは、これらが人間の具体的な「生き方、あり方」として論じられていたことであって、それは近代的世界像において見いだされる普遍的な道徳原理とは異なり、美的価値を内包するものであったということである。
(71)A・G・バウムガルテン(A. G. Baumgarten)は、主として詩に関する考察を通じて、感性によって認識される美と、美を表現したところの芸術という形で、“感性”、“美”、“芸術”が一体化した枠組みを提唱し、知性によって認識される論理学とは区別される形で、感性によって認識されるものの学、すなわち「感性の学」としての美学(aesthetics)を創始した(バウムガルテン 2016)。また、道徳(善)と美の区別を厳密に行ったのはI・カントである。彼は道徳(善)を主として「実践理性」(Praktische Vernunft)の問題、美を主として「判断力」(Urteilskraft)の問題としたうえで、美というものが生理的な意味での快適さとは異なり、個別的な利害関心をこえて、いわば美そのものとして快感情を引き起こすものとした。それを踏まえれば、美は判断に先立って対象そのものに内在するものではなく、鑑賞者の美的判断に伴ってはじめて成立するものであるということになる(カント 1964)。西洋美学をめぐる思想史についてはペルトナー(2017)を参照のこと。
(72)既製品の便器に署名をし、そのまま展示を試みたデュシャンの『泉』(1917)は、既存の芸術概念を破壊するだけの多大なインパクトを備えていた。それは西洋美学が想定してきた美的体験としては意味をなさず、知的な解釈を行うことによってはじめて作品として成立しえるものであった。「現代アート」とは、その意味において、バウムガルテン以来の伝統的な西洋美学の枠組みを解体したところに成立する芸術活動(作品)、として定義することができる。なお、佐々木健一(2019)によれば、“芸術”とはもともと「専門的な技倆(ぎりょう)に関わる」ことを意味する“art”の翻訳語であり、このことから“芸術”と「アート」は本来同じものを指していることが分かるだろう。片仮名語の「アート」が成立したのは、こうした新しい芸術活動(作品)の形式を念頭に、それを古典的な芸術活動(作品)から区別する必要が出てきたからなのである。
(73)佐々木健一(2019)は、ここでの美学における主題の転換を、バウムガルテン以来の芸術=美=感性を前提とした「美的体験」と「美的範疇」から、「解釈」と「美的概念」への移行として整理している。つまり芸術における本質的な問いが、芸術(作品)を鑑賞することで生じる体験のあり方とは何か、優美や崇高を含め美に類型できる範疇とは何かというものから、知的に概念を駆使することで、芸術(作品)にいかなる解釈が可能か、陰気だ、卑屈だといった、これまで「美しい」と見なされなかったあらゆる形容詞を含む形で「美」を拡張したうえで、そこにいかなる概念が成立しているのか、というものへと移行してきたということである。
(74)小崎哲也(2018)は、今日の「現代アート」を成立させるものとして、「インパクト」、「コンセプト」、「レイヤー(鑑賞者が作品を理解、解釈し、そこから多彩な想像、連想を展開していくための補助線となるもの)」という三大要素があると述べる。また「現代アート」を鑑賞していくための具体的視座として、「新しい視覚・感覚の追求」、「メディウムと知覚の探求」、「制度への言及と異議」、「アクチュアリティと政治」、「思想・哲学・科学・世界認識」、「私と世界・記憶・歴史・共同体」、「エロス・タナトス・聖性」、「完成度と補助線」の八つをあげている。
(75)詳しくは小崎(2018)を参照。
(76)例えば、芸術作品を街のいたるところに配置する試みは、従来の「美術館」という概念を解体させるという意味において、確かに「アート」的なものだと言える。しかしそれは、「本来美術館にあるべきものが街角に配置される」という「コンセプト」を通じてはじめて「アート」になるものであって、そこにあるのは依然として「鑑賞」活動である。それは見方を変えれば、「美術館の解体」というよりも「街や風景の美術館化」であり、同時に〈生活世界〉から遊離した「コンセプト」なるものによる、〈生活世界〉の侵食であるとも言える。ここに見られるある種のグロテスクさは、「生き方としての美」の不在、あるいは「鑑賞としての美」による独善性や無神経さに起因するものだと言えるだろう。
(77)このことを考えるうえで重要なのは、「アートワールド」(the artworld)という概念である。「アートワールド」とは、アーティスト、キュレーター、コレクター、学者、評論家、ジャーナリズムなどからなるネットワークのことを指し、A・C・ダントー(A. C. Danto)によれば、1960年代には、何が「アート」で何が「アート」でないのかは、この「アートワールド」が決定するのだとする、「アート」の制度論が盛んに論じられたという。すべてのものが潜在的な「アート」となりうる以上、権威ある何ものかがその判断を観衆に示さなければならない。このことは、おそらくいまなお「現代アート」の実情であると言えるだろう。詳しくはダントー(2018)を参照。
(78)したがってそこでは、死体を切り刻んでホルマリンに漬けようが、動物が飢死するまでを動画に収めようが、「コンセプト」さえ正しければ立派な「アート」となる。筆者が「美的アノミー」と呼んでいるのは、こうした「美意識なき美意識」とも呼べる芸術(作品)への態度のことである。後に見るように、もしそこに「生き方としての美」に関わる美意識があるのだとすれば、人はそうした行いが、あるいはそうした自身の生き方が、〈存在の連なり〉を前にして、はたして「美しい」ものだったのかと問うだろう。ただし逆説的な言い方ではあるが、もしもその人が〈存在の連なり〉に照らしてもなお、そうした芸術(作品)を誇ることができると真に確信するのであれば、その美意識は「本物」であるとも言えるだろう。
(79)もちろん「現代アート」の作品群には、優れたものも数多く存在しているはずである。筆者がここで危惧しているのは、今日の野放図な「アート」のなかで、「生き方としての美」によって支えられた作品、人間存在を正面から見据えた「強度のある〈思想〉」を伴う作品がどれほど試みられているのかということである。われわれはどこか、「価値観は人それぞれ」、「解釈は無限である」といった常套句を逃げ道にして、表現というものを、単なる自意識や自己愛の表出と混同してきた側面はなかっただろうか。そこではどこか、技巧的な斬新さに注力するあまり、美意識自体を強度のあるものとして磨きあげていくことを蔑ろにしてきた側面があったように思えるのである。
(80)もちろん多くの現代の芸術家たちは、自分たちこそが誰よりも高い美意識を備えていると自負しているだろう。だが、美意識というものにも捉え方がある。例えばここでの美意識とは、「アート」になりうる「コンセプト」を構想してく力量でも、芸術(作品)から「コンセプト」を読み取り、「アートワールド」から言葉を借用しつつ、新たな解釈を創出していく力量でもない。それらは「鑑賞としての美」という枠組みのなかだけの「狭義の美意識」であって、われわれが問題にしている美意識とは、そのさらに背景にある、「生き方としての美」に関わるより根源的な美意識の方だからである。
(81)この点は、“美徳”と“美意識”の違いとしても説明することができるだろう。両者はともに、「生き方としての美」に関わるものであるとはいえ、前者は、一般的に社会的な価値規範と深く結びつくところに意味があるのに対して、後者は逆に、必ずしも社会的な価値規範に囚われないところに意味があるとも言えるからである。
(82)人間には、しばしば本人の意思ではどうにもならない、どうしようもなくそうなってしまうというような「生き方」の姿がある。「担い手としての生」を生きるということは、そうしたどうしようもない自らの「生き方」を生き切っていくということでもあるだろう。「芸術家」には「芸術家」の生き方があり、別の人間には別の人間の生き方がある。そして〈存在の連なり〉を想起すれば明らかであるように、それぞれの「生き方」に本質的な優劣など存在しないのである。
(83)【注78】も参照のこと。